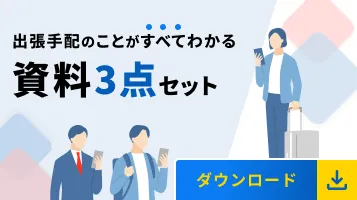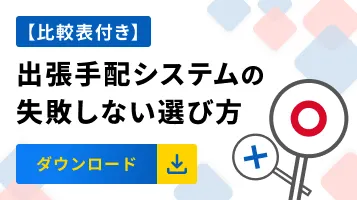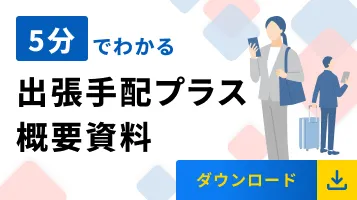社用車の運転で出張する際の労働時間の扱いについて解説

出張者が運転をして出張先に移動する場合、所定の労働時間を超過しがちでしょう。この場合の移動は労働時間となり、残業がつくのでしょうか。
この記事では、出張と労働時間・残業の関係を解説します。
目次
出張と労働時間の関係
労働時間とは、社員が上司の指揮下におかれた時間のことです。労働基準法や会社ごとの就業規則に定められているのが特徴で、決められた時間を超過して残業させた場合、会社側は手当の支給が求められます。
出張は遠方へと赴いて仕事をするため、移動が多く、労働時間の超過を心配する声が多いものです。けれど、出張時の取引先までの移動時間の考え方は、通常の労働時間と同じではありません。
運転中は労働時間にならない
出張は遠方で仕事をするため、取引先への移動だけでも時間がかかります。日帰りの出張の場合、取引先への往復がプラスされる分だけ普段よりも労働時間が長くなる可能性が高いでしょう。けれど、上司から物品の監視や運搬などを命じられておらず、取引先への移動のみを目的とした運転中は労働時間にはなりません。それゆえ、残業手当はつかないのです。
これは、出張先に向かう時間と戻る時間は、自宅から会社に向かうことと何も変わらないという考え方に基づきます。移動にかかる時間がどれだけ長くとも、会社に拘束されているとは考えられず、出張者にとって自由な時間といえるのです。よって、出張時の運転中は労働時間とはならないでしょう。
社員が車を運転して現場へ直行する時間は、労働時間には含まれません。社用車を運転している場合でも同等であり、単なる移動として考えられています。単純に取引先へと向かう運転中は自由ですので、労働時間とはみなされません。
けれども、上司からの指示で移動中にも物品や機密書類等の管理を任されたときは労働時間となります。上司の指示により出張先で使用する資料の作成している場合も同じです。
家に直行せず会社に寄ると休日手当や残業手当がつくことも
出張後に家へと直行せずに会社に立ち寄り、車の返却を上司から指示されている場合には運転時も労働時間として認められます。
所定の労働時間を超過した場合には手当を支給しなければなりませんので、会社への立ち寄りを指示せず、直行直帰を命じている企業もみられます。
所定労働時間の移動の場合は労働時間となる
出張先が会社からそれほど遠方ではない場合、労働時間内に移動できるでしょう。労働時間は社員が働くべき時間ですので、雇用主の指揮下にあります。よって、会社を出て取引先に向かう場合の運転においては、移動も労働時間にみなされるのです。
決められた労働時間内に運転し目的地に到着しても、時間を超過した仕事を命じられた場合には、残業手当が必要となります。残業手当の割増率は25%と高額です。手当の支給によって経営が圧迫される可能性もあるため、会社側は注意が必要です。
会社から仕事を命じられると労働時間
社用車を単純に運転した場合、本来は働くべき時間内でも労働時間とはなりません。けれど、運転中に上司から業務を命じられた場合は運転中も労働時間となり残業代がつくのが特徴です。
運転手としての業務を与えられ、会社の役員を輸送する時間も労働時間ですので、決められた時間を超過して働くと残業となるでしょう。
運転する車に上司が同行しても労働時間となり、残業代が付与されます。この場合は、単なる移動であっても同乗している上司の監視下だと考えられるからです。
本来は移動だけの予定で、運転中に上司からの仕事の指示があったというケースにおいも、運転中が労働時間に変わります。
無料で使える出張管理システムで出張の手間とコストを、経費精算のストレスを大幅カット!
出張時の旅費交通費と通勤費は異なるので注意が必要
運転中の考え方は家から職場に向かう場合と同じです。けれど、定期代やガソリン代などの通勤費と、出張時の旅費交通費は異なります。
旅費交通費とは、企業において業務上必要となる遠方へと出張した場合に支給される出張旅費のことです。移動のための交通費や宿泊費のほかに、出張手当も旅費交通費に含まれます。旅費交通費は会社の出張旅費規程に定義されていますので、支給される範囲は会社ごとに異なるのが特徴です。
一方、社員が勤務地へと通勤するための費用が通勤費で、自宅を出発してから会社に到着するまでにかかる費用をいいます。このとき、気を付けるべきは点は自宅を出発して出張先へと直行する際の費用でしょう。これは、通勤費ではなく旅費交通費となります。通勤費は全額給与としてみなされるのに対し、旅費交通費は非課税となります。
旅費交通費として処理すると法人税が節約できますので、旅費交通費の支給は会社にとってメリットが大きいといえるのです。
旅費交通費を節約する方法
新幹線や飛行機を使って出張を命じると、旅費交通費がかさむと感じることもあるでしょう。
けれど、社員自らが運転して出張先へと移動すると、事故に遭遇する可能性が高まります。早朝や深夜の移動で事故に巻き込まれた事例も多く、トラブルにも発展しかねません。
そういった理由から、社員から「運転ではなく公共の交通機関を使いたい」との相談も相次いでいるのです。
そこで、エルクトラベルを利用した出張手配をおすすめします。エルクトラベルを利用すると旅費交通費の大幅な節約が可能です。ここからは、エルクトラベルの詳細について解説しましょう。
航空便を使った移動が格安に
エルクトラベルを利用すると、国内航空便での移動にかかる料金が抑えられると評判です。
多くの旅行代理店が出張パックなどを打ち出し、格安プランを提供していますが、この場合には利用できる時間などが限られていることが多いといえます。
出張先での仕事が終わっているにもかかわらず電車の時間を待つために時間をつぶす必要に迫られることもあり、社員の身体的負担が増えてしまうのが問題です。
エルクトラベルの場合、出張パックはもちろんのこと変更可能な独自の割引も利用が可能ですので、急遽予定が変わってしまう場合でも安く利用できると評判です。
海外航空券の発券手数料も抑えられる
一般的に飛行機の利用は交通費がかさむと考えられています。
海外航空券代のほかにも発券手数料がかかるため、交通費が高額になりやすい点が問題です。
ほとんどの旅行会社で料金連動型の発券手数料が採用されていますので、遠方への出張になればなるほど発券手数料が高くなってしまいます。
その点、エルクトラベルは発券手数料が一律です。海外出張でも発券手数料が高くなりすぎることがなく、安心して利用できると高く評価されています。
月額利用料が無料
出張手配サービスを使う際、気になるのが月額利用料でしょう。
交通費や宿泊費が節約できても、月額利用料がかかりすぎてしまうと結果的に高くなる場合があります。
エルクトラベルでは、月額利用料が無料ですので余分な費用が抑えられるのが魅力です。出張の回数が少ない会社の場合でも気軽に利用できることから、導入している会社も多いといえるでしょう。
勤怠管理も簡単に
エルクトラベルでは社員それぞれの出張手配の請求を一括でしているのが特徴です。
社員がどの時刻の電車に乗り、どのような出張をしたのかが把握できるようになりますので、スムーズな勤怠管理が可能になります。
経理の負担を軽減
出張が多い会社では経理の労働時間の長さも問題とされています。
なぜなら、出張時の後日精算業務や出張費の仕訳など、出張が増えるたびに経理の仕事量が増大するからです。
エルクトラベルを出張手配を行うとすべての社員の利用分を一括で会社に請求します。
後日精算業務そのもののカットが可能になることから経理の労働時間が大幅に短縮できるでしょう。労働時間が短くなることで人件費の削減も可能になるのです。
自分で運転をさせる際には労働時間に気を付けよう
社員に自ら運転を命じて取引先に向かわせる場合でも、移動中は労働時間になりません。そのため、移動に時間がかかっても残業とはなりにくいでしょう。
けれど、移動中に仕事を課した場合には労働時間へと変化します。
その結果、残業代がつくことがありますので注意が必要です。加えて、長時間の運転は疲れやすく身体的な負担がかかります。
社員に出張先で高いパフォーマンスを発揮してもらうためにも、新幹線や飛行機を使った移動が推奨されるのです。
エルクトラベルで出張手配を行うと、経費を削減しながらスムーズな出張が可能になります。
社員の勤怠管理も簡単にできますので、出張時の不正なども防げて安心です。エルクトラベルの出張手配を導入し、便利で快適な出張の実現と業務効率の向上を目指してみませんか。
関連記事:
出張旅費規程で節税ができる?旅費規程のメリットと作成時のポイントとは
出張に伴う宿泊・日帰り手当の基準を紹介
新幹線での日帰りはNG?宿泊でも費用を抑えて出張の成果をアップさせる方法
定義がポイント!出張手当で会社の手間と経費を削減する方法
休日出勤扱いにもなる?労働基準法における出張を徹底解明
労働基準法のチェックを!出張における労働時間の扱いとは
無料の出張管理システム「出張手配プラス」で、出張手配や経費精算の効率化を!

出張手配プラス サービス概要資料
出張手配や出張費の可視化には、無料の出張手配管理システム「出張手配プラス」がオススメです。出張管理・予算管理など、毎月の手間やコストを大幅削減しながらリスク管理ができる仕組みを紹介します。
この記事を書いた人

エルクトラベル編集部
- プロフィール :
-
出張手配専門旅行会社の株式会社エルク(エルクトラベル)のメディア編集部。
これまで2,700社以上の出張関連業務の効率化を支援してきた実績を活かし、出張者はもとより出張に関わる経理や総務などのバックオフィス部門にも役立つビジネス情報を発信しています。