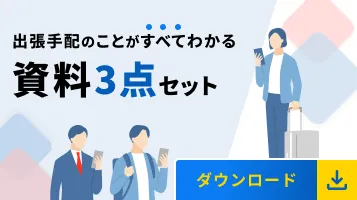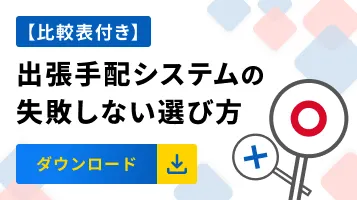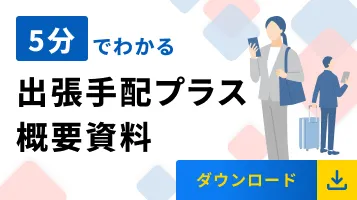内部統制とは?4つの目的・6つの要素を解説!メリットを押さえて適切なシステム整備を

企業が事業を継続するうえで、欠かすことができない要素の一つが「内部統制」です。
組織としての企業を健全に維持するために必要なものですが、どのような目的やメリットがあるのかは意外と知られていないかもしれません。しかし、きちんと理解しないままでは、内部統制に向けて仕組みを整備するのは難しいでしょう。
今回は内部統制の実施に必要な項目だけではなく、目的や重視すべきメリットなども含めて解説します。
本記事の内容:内部統制を行ううえで意識しておきたい目的・メリットの理解
目次
- 内部統制とは?
- 内部統制の4つの目的
- 内部統制の4つの目的の関係
- 内部統制の6つの基本的要素
- 内部統制の3点セットとは?
- 内部統制に関わる人とその役割は?
- 内部統制システムが必要となる会社は?
- 内部統制を行うメリット
- メリット1:業務内容や業務フローの可視化・整備ができる
- メリット2:財務状況の見える化・把握につながる
- メリット3:社内ルールやガイドラインの整備につながる
- メリット4:不正やミスの起きやすい業務フローやルールの撲滅につながる
- メリット5:社員モチベーション・組織の業績向上につながる
- メリット6:企業の社会的信用の向上につながる
- 内部統制を構築する流れ
- 内部統制を強化する手順
- コーポレートガバナンスを強化する方法
- 内部統制をかなえるためのIT推進とは?
- 内部統制によって企業価値を高めよう
内部統制とは?
内部統制とは、企業が健全かつ効率的に事業活動を続けるための仕組みのことです。全ての従業員が遵守すべきルールのため、一般的に内部統制は企業内で行われるほとんどの業務に組み込まれています。
内部統制をしっかりと整備することで、社内の不祥事を防止し、業務の効率化や法令遵守、資産の保全を図ることができます。
ここで重要となるのは「目的やメリットを理解して運用されているか」という点です。
金融庁による内部統制の定義
金融庁は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」で、内部統制の定義と、4つの目的、6つの基本的要素を定めています。
内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。
内部統制とコーポレートガバナンスとの違い
内部統制と類似した言葉として、コーポレート・ガバナンス(企業統治)があります。
コーポレート・ガバナンスは、企業内で働く従業員のみならず、株主や債権者などのステークホルダーが関わる概念です。企業が企業価値向上に努め、株主などのステークホルダーに最大限の利益を還元できるような取り組みを行う経営管理統制の仕組みが、コーポレート・ガバナンスだといえます。監査といった外部からの評価も意識する必要があるでしょう。
一方で、内部統制は従業員が守るべき組織内のルールや仕組みです。外部的視点より内部に目を向ける視点となります。その点において違いがあります。
<関連記事>
コーポレートガバナンスの意味とは?社内への浸透を図り健全な経営を
内部統制とコーポレートガバナンスの共通点
内部統制とコーポレートガバナンスの共通点は、「健全な経営を継続するためのルールや仕組み」という目的です。いずれも不正防止や疑問点を追及された際に情報開示できる状態にするといった目的があります。
意味は混同されがちですが目的は共通しているため、内部統制を強化することがコーポレートガバナンスの強化にもつながります。両方を区別して意味を把握したうえで、健全な経営を目指しましょう。
内部統制の4つの目的

内部統制はただ実施されるべきではありません。目的を意識して実施してこそ、本来の効果を発揮するからです。
企業における内部統制の目的について、金融庁は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」の中で、4つの項目を列挙しています。
内部統制の4つの目的
- 業務の有効性および効率性
- 財務報告の信頼性
- 事業活動に関わる法令などの遵守
- 資産の保全
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
1.業務の有効性及び効率性
1つ目は、「業務の有効性および効率性の向上」です。
事業活動の目的を達成するためには、業務の有効性や効率性を高めることが必要不可欠です。
内部統制が適正に行われることで、「時間」「人」「モノ」「コスト」の活用が合理的に行われているかどうかをチェックする機会が生まれ、結果的に個々人の業務の合理化や組織全体の効率化につながります。
2.財務報告の信頼性
2つ目の目的は、「財務報告の信頼性が高まる」という点です。
法令に従った内部統制がきちんと行われることで、財務報告(決算書)が適切に作成されるようになります。財務報告の信頼性は、企業の社会的信用につながるため、適正な内部統制は企業の信用を向上させるでしょう。
財務諸表及び財務諸表に影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性や透明性を確保することが重要です。
3.事業活動に関わる法令等の遵守
3つ目は「事業活動に関わる法令等の遵守」です。
事業活動に関わる法令やその他の規範の遵守を怠ると、何らかの法令違反により罰せられことがあるでしょう。法令違反によって社会的信用を大きく失うと事業の継続ができなくなることもあるため、 企業を存続させる上では、内部統制によって従業員全体で法令やその他の規範の順守を徹底することが必要です。
4.資産の保全
4つ目の目的は、「資産の保全」です。
資産が不正にまたは誤って取得、使用や処分された場合には、企業の財産や社会的信用を大きく失う可能性があります。また、企業が出資等を受けて活動している場合、経営者はこれを適切に管理する責任があります。
適正な内部統制のもとでは、資産の取得や使用、処分について正当な手続きで行われているかをチェックされます。内部統制を整備し、不正な方法での運用を排除することで、健全な企業活動と企業の資産保全を行うことが可能です。
内部統制の4つの目的の関係
内部統制の 4 つの目的は、それぞれ固有の目的ですが、お互いに独立して存在するものではなく、相互に密接に関連しています。 内部統制は業務に組み込まれ、企業内の全ての者によって遂行されるプロセスであり、いずれかの目的を達成するために構築された内部統制であっても、他の目的のための内部統制と共通の体制になったり、お互いに補完しあう場合があります。
したがって、内部統制を有効かつ効率的に構築しようとする場合には、4つの目的の関連性を理解した上で、内部統制を整備し、運用すると良いでしょう。
内部統制の6つの基本的要素

内部統制において、重視すべき基本的要素について金融庁は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」の中で、以下の6つを挙げています。
内部統制の6つの基本的要素
- 統制環境
- リスクの評価と対応
- 統制活動
- 情報と伝達
- モニタリング
- ITへの対応
6つの基本的要素について以下に詳しく解説します。
1.統制環境
1つ目の統制環境は、組織内のすべての者の内部統制に関する意識やそれを取り巻く環境・社風などを表し、その他5つの基本的要素の基盤となる最も重要な基本的要素です。
統制環境として具体的には、企業の誠実性や倫理観、経営者の意向および姿勢、経営方針や経営戦略、組織構造や慣行、人的資源に対する方針と管理などがあげられます。
2.リスクの対応と評価
2つ目のリスクの対応と評価は、事業目標の達成の妨げになる可能性がある事柄をリスクとして識別、分析および評価をして適切に対応をする一連のプロセスのことを指します。
事業目標の達成にどのようなリスクが存在するか識別し、どのくらいの規模なのかや発生可能性、目標達成にリスクが与える影響などを議論し、回避すべきか、低減すべきかなど適切な対応を選択します。
3.統制活動
3つ目の統制活動とは、経営者の指示した事項が確実に実施されるための仕組みづくりを指します。具体的には、権限や職責の付与、職務の分掌、社内規定の設定や業務マニュアルの作成と整備などです。
統制活動は、業務プロセスに組み込まれるべきもので、企業内のすべての者が遂行することで機能します。例えば、出張の稟議や承認を得るプロセスは、 成果の見込めない無駄な出張の防止やカラ出張などの不正を抑止するための統制活動にあたります。日常で行われている社内手続きの多くは、統制活動に含まれています。
4.情報と伝達
4つ目の情報と伝達とは、社内外にかかわらず関係者相互で的確に情報を共有できる体制の構築を意味します。
内部統制を実施するためには、必要な情報の識別、把握および処理をし、企業内外の関係者相互に適切なタイミングで正しく伝達される必要があります。 一連のプロセスや情報システムの整備によって、適切で迅速な情報伝達や企業内部の不正行為の防止を行うと同時に、情報漏えいのリスクを減らすことができます。
5.モニタリング
5つ目のモニタリングは、内部統制が有効に機能しているかを継続的にチェックし評価するプロセスのことです。
モニタリングには、経営管理や業務改善などの日常業務に組み込まれて行われる「日常的モニタリング」と、業務から独立した視点で経営者や取締役会、監査役や内部監査などによって実施される「独立評価」があります。両者は個別にまたは組み合わせて実施されます。
6.ITへの対応
6つ目のITへの対応は、事業目標を達成するためにあらかじめ適切な方針や情報管理規定などの手続きを定め、それを踏まえて組織内外のITに対して適切に対応することです。「対応」「利用」「統制」の各プロセスで構成されます。
広くITが浸透している現代においては、ITへの対応は不可欠です。内部統制の4つの目的の達成に向けて、内部統制に利用するシステムの管理・開発・保守を行ったり、アクセス権限を管理するなどして、6つの基本的要素をより機能的に実行できる仕組みを確保していくことが大切なのです。
内部統制の3点セットとは?
内部統制を構築していくためには、「内部統制の方針策定」→「現状確認」→「評価」→「見直し」→「報告」といったステップで進めますが、 その際に必要となるのが「業務記述書」「フローチャート」「リスクコントロールマトリックス(RCM)」の3点です。一般的に内部統制の3点セットと呼ばれるもので、作成することにより全体の業務を可視化し、正しく評価できるようになります。
業務記述書
業務記述書とは、それぞれの業務に関する内容や手順、実施者、利用システムなど、その業務に関連する情報を言語化し文章にした書類のことです。リスクコントロールの把握や業務内容の理解度などを確認できます。
フローチャート
フローチャートは、会社の部署や部門ごとに業務の流れを図で表した書類です。一連の流れを視覚的に把握できるため、業務の全体像の把握が容易になり、リスクの識別に役立ちます。
リスクコントロールマトリックス(RCM)
リスクコントロールマトリックスは、業務上のリスクと、そのリスクへの対応状況をまとめた表のことです。リスクに対する必要な対応と進捗状況が明確化し、内部統制の評価に役立ちます。
内部統制に関わる人とその役割は?
内部統制は経営陣だけでなく全従業員が関わるものですが、それぞれの立場によって異なる役割を持っています。立場別の役割について見ていきましょう
経営者
経営者は、取締役会で決定した内部統制の基本方針に基づき内部統制が正しく機能するように整備・運用をする責任と役割があります。また、最終的な評価と代表者として内部統制報告書を提出する義務があります。
取締役会
取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、経営者による内部統制の整備・運用について、正しく実施されているか監視する役割があります。
監査役・監査委員会
監査役・監査委員会は、取締役や執行役の職務執行に対する監査の一環として、独立した立場から内部統制の整備や運用状況を監視、検証する役割と責任があります。
内部監査人
監査役などとは異なり、組織の内部から内部統制の整備や運用状況の評価を行い、必要に応じて改善を促す役割を担っています。独立した立場の監査役と、組織内から評価を行う内部監査人が、それぞれの視点で内部統制をモニタリングします。
従業員
内部統制は、全従業員が遵守・遂行するルールです。社内のあらゆる業務に組み込まれているため、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員などすべての従業員が内部統制の方針や仕組みを正しく理解し実践していく必要があります。
内部統制システムが必要となる会社は?
会社法や金融商品取引法によって、大会社や上場企業は内部統制システムの整備が義務付けられています。一方で、義務付けられていない会社でも業務効率化や企業価値向上につながるため、どの企業にとっても必要な取り組みと言えるでしょう。
大会社かつ取締役会設置会社
取締役会を設置している大会社は、会社法第362条5項で内部統制の整備が義務付けられています。会社法で定められている大会社とは、最終事業年度に係る賃借対照表の資本金が5億円以上、または負債額が200億円以上の会社を指します。
上場企業
上場企業については、金融商品取引法第24条において事業年度ごとに内部統制報告書の提出を義務付けています。また、上場を目指す企業においても内部統制の整備は必須となります。 東京証券取引所が定める有価証券上場規程第207条で上場審査基準として「コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること。」が挙げられており、上場を目指す段階から取り組む必要があるでしょう。
内部統制を行うメリット
法律によって内部統制の整備が義務付けられている企業以外でも内部統制を実施することで、企業として得られるメリットはいくつもあります。どのようなメリットがあるのかを理解したうえで、適切なルール作りなどを行うことが重要です。
ここでは、内部統制を行うメリットについて見ていきましょう。
メリット1:業務内容や業務フローの可視化・整備ができる
内部統制は、現場の業務も含めて、しっかりとしたルールと仕組みづくりを行うことにつながります。
経営陣が実際の業務を把握することができれば、より合理的かつ効率的なシステムを構築する手助けになるでしょう。
メリット2:財務状況の見える化・把握につながる
業務の可視化だけではなく、財務に関する情報についても詳細を把握しやすくなります。
財務状況は経営の根幹に関わるものであり、適切に把握されていることが重要です。内部統制を徹底することで、経営状況を正しく認識し、適切な経営判断を行うのに役立つでしょう。
メリット3:社内ルールやガイドラインの整備につながる
内部統制には、全従業員が遵守すべき社内ルールやガイドラインの策定が欠かせません。
内部統制を強化することで、日々の業務フローから従業員全員に適用する社内ルールに至るまで、一挙に見直し改善を行うことができます。また定期的に見直しを行うことで、従業員への浸透を促すこともできるでしょう。
メリット4:不正やミスの起きやすい業務フローやルールの撲滅につながる
内部統制を徹底することで、従業員による不正を招きやすい業務や資産管理などのリスクを軽減できるようになります。また情報漏えいなどの社会的信用を失うような事態を防止する効果も期待できるはずです。
法令遵守に関する意識を浸透させ、基本的なプロセスとしてルールに組み込んでいくことが大切です。
メリット5:社員モチベーション・組織の業績向上につながる
内部統制には、従業員が効率的に働ける仕組みを作り上げる側面もあります。
そのため、業務の工程を改善し、適正な評価基準が構築されることで、従業員のモチベーションも上昇するでしょう。また、組織内における共通のルールが設定されることで、組織内における信頼を築きやすくなります。従業員同士の協力が円滑に進むことによる業績向上も見込めるのです。
メリット6:企業の社会的信用の向上につながる
内部統制の整備と強化によって、健全な業務遂行や従業員のモラル向上を見込めます。ルールを整備し、従業員への遵守を徹底すれば、市場における企業の社会的信用の向上にもつながるのです。
従業員からの反発を受けるといったデメリットもありますが、あくまで一時的なものであり、最終的には企業の価値を高めるものになるでしょう。
内部統制を構築する流れ

実際に内部統制を構築する際は、上記で紹介した内部統制の目的や基礎的要素を把握して理解する必要があります。
目的と基礎的要素を踏まえたうえで、具体的な構築の流れについて一つずつチェックしてみましょう。
内部統制の方針策定
第一におこなうことは、内部統制の方針策定です。目的を定めることで具体的な活動内容を目指しやすくなります。
たとえば、決算や財務報告に関する内部統制を構築したい場合は、上記で紹介した「業務記述書」「フローチャート」「リスクコントロールマトリックス(RCM)」の3点セットがカギです。ただし3点セットは多くの企業が用いており、3点セットのみでは正常な機能を保てるか不安な企業も多いでしょう。そこで監査人と相談のもと、独自のチェックシートを作成・活用することで内部構成の構築につながります。
方針策定や目的は具体的なほどトラブルやリスクを回避しやすくなるため、時間をかけてでも取り組む部分です。対象となる部署の業務規定や暗黙の了解となっているルールをまとめて、リスクを分析しつつどのように改善していくか方針を決めます。
また、構築の過程から内部統制の「文書化」を心がけましょう。文書化すれば業務のモニタリングもスムーズになり、適宜ルールを作りやすくなります。文書化には重要な理由がもう一つあり、企業側が内部統制を構築したと思っていても、いざ監査で指摘された際に文書化されていなければ内部統制したという事実を示せません。そのため対外的に「内部統制を構築している」と表すためにも必要な工程です。
2種類のタイプで内部統制の文書を作成
内部統制の文書化には、「集中型」と「分散型」の2種類があります。
「集中型」は、内部統制専用のプロジェクトチームを組み文書化を進めることを指します。人員が割かれるため通常業務に支障が出る可能性がありますが、短期間で集中的に取り組むことで業務管理しやすく、文書化を効率的に進められる方法です。
「分散型」は、部署ごとに文書化を進める方法であり、専用のプロジェクトチームによる文書化はありません。内部統制構築の対象部署による文書化であり、メンバーが普段から担当している業務に関わっていることから、滞りなく文書化が進むことが期待できます。
内部統制の現状評価
内部統制の方針を策定後は、現状の評価に移ります。「業務記述書」「フローチャート」「リスクコントロールマトリックス(RCM)」の3点セットを用いて、業務内容ごとのリスクを把握しましょう。
リスクや問題点が表れたらその都度記録・モニタリングで対策を練り、対象部署や社内全体に周知して回避を目指します。
すべてのリスクを受け入れると対策が追い付かないこともあるため、リスクをレベル別や対象部署ごとに分類して、危険度や重要度の高いリスクから改善することが基本です。
内部統制の運用
内部統制の方針と評価が完了したら、実際の運用で内部統制の機能を確認します。モニタリングの実施中は適宜記録して、新たな内部統制の有効性を評価します。
モニタリングは内部統制の6つの基本的要素で紹介した「日常的モニタリング」と「独立的評価」の2種類の手法でおこなわれます。モニタリングを実施して早期に課題を発見することで、内部統制の効果をさらに向上させられるでしょう。
モニタリング中では、定期的に評価や分析、改善を繰り返します。3点セットはモニタリング中の評価にも活用できるため、問題点や不備が見つかれば3点セットを参考にしつつ改善策を練って、本格的な運用に備えましょう。
内部統制報告書の作成&提出
モニタリングの結果判明後は、速やかに内部統制報告書を作成します。改善しない結果になったとしても内部統制報告書の提出は義務であるため、作成は必須です。
内部統制報告書の最終的な評価にも3点セットを活用することで、さらに状況に応じた報告書が作成できます。
内部統制報告書の提出後は、内部統制の構築が成功した場合は運用を維持し、改善点があれば再び対策を練ります。定期的に監査を続けることで、いち早く問題点を見つけて運用効果の向上を目指せるでしょう。
内部統制報告書の作成方法
内部統制報告書には、以下の事項について詳しく記載します。
内部統制報告書の記載事項
- 会社の基本情報
- 内部統制の基本的枠組み
- 評価の範囲や基準日、手続き
- 評価結果
- 付記事項と特記事項
報告の表現に関する様式は定められておらず、会社のフォーマットを利用します。内部統制報告書には3点セットを資料として用いることが多いため、3点セットの作成時も不備のないよう気をつけることがポイントです。
内部統制を強化する手順
内部統制に取り組んだ経験のある企業でも、効果が数値に表れないことも珍しくありません。内部統制をさらに強化したい場合は、以下の手順をぜひ参考にしてください。
リスクの洗い出し
考えうるリスクを洗い出して可視化することは、新たに内部統制を構築する場合でも、現在の内部統制を強化する場合でも重要となる手順です。あらかじめ起こりうるリスクを把握していれば、万が一不正や事故が発覚した場合でも早々に対処ができて最小限の損失に抑えられます。
財政状況やキャッシュフローのみでなく、特定の取引先からの技術等に対する依存についてなど、まずは分野に関係なく業務全体のリスクを挙げましょう。リスクを洗い出して抽出したら、次はリスクの分類に移ります。「社内」に関することか「社外」のリスクであるか、偶発的なものかなど、さまざまな種類別に分類して、それぞれ損失・影響が大きい順や発生頻度の高い順に評価します。リスクの対処法は、種類別に分けて優先順位の高い順におこなうことが基本です。
また業務内容はもちろん、災害時の対処法や安否確認システムの実装といった有事の際の対応もリスク管理の一つです。
社内規定の整備
企業が抱えているリスクが判明したら、対策となる社内規定を整備しましょう。社内規定は存在していてもすでに形骸化して誰も守っていない状況である企業も珍しくないため、まずは社内規定やマニュアルの整備と周知が必要です。
まず役職のある社員や経営陣がマニュアルに沿うことで、社員も社内規定を守るべきものと認識します。
内部監査の実施
内部監査は内部統制において重要なポイントです。内部監査の目的は不正防止や経営目的達成に向けた改善策の模索、業務効率化などが挙げられるため、業務に関する内容の監査が多い傾向にあります。
内部監査専門の部門を設けて内部監査を実施することで、公平な立場からコンプライアンス違反やリスクマネジメントの適切性などを評価し、助言します。結果的に内部統制の強化につながり、経営の基礎がさらに強固なものとなるでしょう。
また、内部監査を実施する際は、経営陣から独立した人材でチームを組むことが重要です。内部監査は公平な立場であることが前提となるため、経営陣に取り込まれるような内部監査では効果が薄れてしまいます。
<関連記事>
内部監査とは?外部監査との違いや目的、流れ、実施のポイントをわかりやすく解説
ワークフローシステムの導入
ワークフローシステムとは、稟議申請書や通知書などワークフロー上の承認プロセスを電子化するシステムを指します。ワークフローシステムを導入することで、在宅勤務中でも押印のために出社する必要もなく、過去の書類検索も簡単になるといった業務効率の大幅な向上が期待できます。
申請を経費精算や支払関連と紐づけることも可能であり、予算管理ツールとしての側面もあることから、上場企業以外でも積極的に取り入れるべきシステムの一つです。
しかし、新たなシステムを導入する際の課題ですが、システムを扱う社員が操作方法を覚えたり業務内容の変更を余儀なくされたりなど社員が感じるデメリットが多く、浸透までは必ず時間を要します。適宜マニュアルを作成し社内研修で理解を深めるといった対策が求められるでしょう。
ERPシステムの導入
ERPシステムとは、「ヒト・モノ・カネ」といった、企業の経営資源の情報を集約して活用するシステムを指します。情報を集めることで業務に必要なデータ全般の管理が容易になり、業務の透明化や迅速な経営判断の材料となります。
ERPを活用してデータを一元管理することで重複処理を避けたり、業務の透明化による不正行為の予防になったりなど、内部統制の強化につながります。
内部統制を強化する目的でERPを導入する場合は、財務会計や委託契約の管理、システム運用などの機能が備わっているERPがおすすめです。上場企業で利用されているシステムから選ぶことも失敗しにくい方法の一つです。
また、ERPシステムを導入した際は、最初にセキュリティ設定を完了させることが重要です。初期設定を済ませないと誰もがすべてのデータにアクセスできる状態になってしまうため、すぐにアクセス権限の設定や本番環境・開発環境の分離などについて設定しましょう。
取締役会の設置
取締役会とは、3人以上の取締役による業務執行の意思決定の場です。重要な財産処分や譲受け、支配人の選任や解任など経営の根幹となる部分の意思決定を担うため、公開会社や監査役会設置会社は取締役会を設置するように会社法で定められていますが、条件に当てはまらない会社でも設置が可能です。
取締役が正常な職務執行に務めているか監督する役割があり、特定の取締役によるワンマン経営を防止できる機関でもあります。
株主総会より迅速に経営方針を定められるのみでなく、経営陣を監督することから取引先の信用も得やすいといったメリットが挙げられますが、設置には最低でも取締役3人と監査役1人が必要になり、役員報酬も発生します。資金繰りに悩んでいる設置義務のない企業の場合は、よく検討を重ねましょう。
最高責任者の不参加で開催する取締役会の効果
取締役会では、企業の最高責任者であるCEOが出席することが一般的です。しかしCEOは取締役会において大きな権力を持つ人物であり、たとえ経営方針に適していない意見を発言しても、ほかの役員が大きく反論できずそのまま決定してしまうおそれがあります。
そのため権力に影響せずさまざまな意見の中から客観的に判断したい場合は、最高責任者が取締役会に参加しないことも選択肢の一つです。
コーポレートガバナンスを強化する方法
内部統制とコーポレートガバナンスの目的には共通点があるため、コーポレートガバナンスを強化することが内部統制の強化にもつながります。
コーポレートガバナンスを強化して内部不正を防止することで企業の透明性も周知できて、企業価値が上がりステークホルダーの利益も守られます。
取締役会のみでなく、株主や顧客など多くの視線を向けられても問題ないような透明性の高い経営にするために、コーポレートガバナンスの強化を目指しましょう。
内部統制の強化
内部統制とコーポレートガバナンスは似た言葉ですが、目的は「健全な運営を目指すこと」で同じといえます。内部統制を重視して強化することで、コーポレートガバナンスの強化にもつながるでしょう。
内部統制を強化する方法であるリスクの洗い出しや社内規定の整備を徹底することも、コーポレートガバナンス強化に大きく影響します。
経営陣と社員が企業で定められているコンプライアンスに則って活動しているか、常に管理できるような体制が求められます。
社外取締役や社外監査役などの設置
経営者を監視して暴走を防ぐことが目的の一つであるコーポレートガバナンスでは、社外取締役や社外監査役など、会社外である第三者の役員を設置することも強化する方法の一つです。
| 社外取締役 | 社外から経営を監督する人物で、業務の執行も可能 |
|---|---|
| 社外監査役 | 社外から業務の適法性を監査する人物 |
| 報酬委員会 | 社外取締役や社外監査役から構成された、役員の報酬を決める委員会 |
特に報酬委員会は全体の過半数以上が外部の役員であるため、対外的にもコーポレートガバナンスを重視している企業という証明になるでしょう。
執行役員制度の導入
執行役員制度とは、本来取締役がおこなうべき業務執行を執行役員に任せることを指します。
役員が決めた経営方針を取締役の代わりに執行するため、取締役といった役員は定めた経営方針を執行役員に伝えて遂行してもらいます。その際に経営に関する不審点があれば、執行役員は直接経営陣である役員に追及できるため、業務に反映される前に不正を阻止でき、結果的にコーポレートガバナンスの強化となります。
従業員へのコーポレートガバナンス周知
社員のなかにはコーポレートガバナンスがどのようなもので、自社の方針を知らない方も多いでしょう。まずは社員の意識を高めるために、コーポレートガバナンスを周知することがおすすめです。
社員の意識を高めることで、プロセスの遵守や現在の体制、経営に対して監視する意識が芽生えるため、結果的に役員の不正抑止につながりやすいです。また企業の取組が明確になることから企業価値も上がり、業務に対するモチベーションアップや企業に対するエンゲージメント向上も期待できます。
コーポレートガバナンス強化につながるツールの導入
コーポレートガバナンスは、「勤怠管理システム」や「ワークフローシステム」などのツールでも強化できます。
勤怠管理システムとは出勤と退勤、残業などの管理ができるシステムで、社員の労働時間の把握が容易になるツールです。状況を見て残業を減らすといった働き方の改善・予防もできるため、労務管理を徹底する場合に導入がおすすめされます。
ワークフローシステムとは、業務を遂行する一連の流れを管理するシステムです。業務ごとに責任者が割り当てられて、いつどこで不正が発生したのか判明しやすく、業務の可視化と透明化を目指せます。
内部統制をかなえるためのIT推進とは?
先に述べた、金融庁の掲げる4つの内部統制の目的(1.業務の有効性及び効率性、2.財務報告の信頼性、3.事業活動に関わる法令等の遵守、4.資産の保全)の達成のために、社内のIT化を進める企業も少なくありません。健全な経営のためにシステム・ツールの検討も有効です。
業務システムを変えることは効率化・コスト削減だけでなく、そもそも、不正やミスがおこらない業務フロー、社内規定遵守の徹底、情報漏えいなどのリスク排除にも役立ちます。経営視点で見ても、おおきく効果が見込めるものなのです。
すでに一般的になった経費精算システムのほか、在庫管理システム、出張管理システムなど、不正の温床となりがちなカテゴリーから導入を始めるとよいでしょう。
内部統制によって企業価値を高めよう
内部統制を実施することは、業務の効率化や業績向上といった企業価値を高める結果につながるだけではなく、社会的信用を上げたり企業イメージを改善したりする効果も期待できるものです。
また、従業員による不正を防止し、企業資産の保全につながる面もあるため、法律によって実施が義務化されていない企業でも、適切な内部統制の実施は企業の成長に不可欠だといえます。健全な経営のために経費精算システムや在庫管理システム、出張管理システムなど不正の温床となりがちなカテゴリーからシステム・ツールの導入を進めていき、自社に合った仕組みを整えてみましょう。
出張の内部統制強化には出張管理システムを!無料の出張手配・管理システム「出張手配プラス」

出張手配プラス サービス概要資料
出張の内部統制強化には無料の出張手配管理システム「出張手配プラス」がオススメです。出張手配や出張費を可視化し、不正防止や危機管理にも役立ちます。出張管理・予算管理など、毎月の手間やコストを大幅削減しながらリスク管理ができる仕組みを紹介します。
この記事を書いた人

ナナイ【行政書士・FPライター】
- プロフィール :
-
行政書士・FPの資格を保有。WEBライティング歴8年のライターです。
その知識を活かしてビジネスや相続、不動産などのジャンルを得意分野としており、多岐ジャンルのコラムを執筆しております。
編集者

エルクトラベル編集部
- プロフィール :
-
出張手配専門旅行会社の株式会社エルク(エルクトラベル)のメディア編集部。
これまで2,700社以上の出張関連業務の効率化を支援してきた実績を活かし、出張者はもとより出張に関わる経理や総務などのバックオフィス部門にも役立つビジネス情報を発信しています。